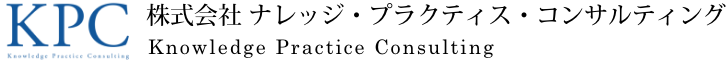落合博満監督のオレ流叱りかた~こうやって叱れば部下は反論できない?!
●はじめにひと言
プロ野球のペナントレースも7月が終わり、
それぞれの球団で、明暗が分かれてきているようです。
セ・リーグで言えば、
阪神タイガースが独走しそうな雰囲気がありましたが、
ここにきて、2位の中日ドラゴンズが11連勝と
相当な追い上げを見せています。
ということで、今回は、中日ドラゴンズの落合監督ネタで
書いてみたいと思います。
(あのまま中日が弱いままだったら、
書き溜めた落合ネタが全部ボツになるんじゃないかと
心配していました・・・。)
●落合監督、谷繁捕手を叱る!
昨年の話になります。
中日ドラゴンズの優勝が決まった次の日だったかと思います。
あるラジオ番組でドラゴンズの選手達が
優勝までの経緯や喜びの気持ちなどについて
インタビューを受けていました。
その中で、
「今年、一番印象に残っていることはどんなことですか?」
と聞かれた谷繁選手はこんな風に答えていました。
「今年一番印象に残っていることはですね。
一度だけ落合監督に怒られたことがあるんですよ。
6月の東京ドームでのジャイアンツ戦で川上が投げていて、
高橋由伸にホームランを打たれたんです。
そのときだけはえらく落合監督に怒られましたねぇ。
それが一番印象に残っています。」
あまり選手を叱らないという印象のある落合監督ですが、
叱るべきところは叱っているんですね。
●これぞ、うまい叱りかた!
なぜ、落合監督は、ホームランを打たれて
谷繁選手を叱ったのでしょう?
中日ドラゴンズの場合、
落合監督が就任して以来、昨年も今年も、
チームの方向性は、「守り勝つ野球」です。
恐らく、あのときの谷繁選手の配球は、
試合の流れや、相手バッターの特徴などを考えたら完全に、
「ポカミス」だったのでしょう。
配球ミスをして、
打たれなくてもいいホームランを打たれた谷繁選手は、
チームの方向性としての「守り勝つ野球」に
沿わないことをしたと落合監督の目には映ったのだと思います。
あまり叱らない印象の落合監督も
チームとしての方向性に沿わないことをした選手に対しては、
しっかりと叱っているのではないかと思うのです。
恐らく落合監督の就任以来、
中日ドラゴンズで、打てなくて叱られた選手は
まずいないのではないかと思っています。
「打ち勝つ野球」を目指しているわけではないのですから。
それに対して先ほどの谷繁捕手のように、
守りの面でのミスをして叱られた選手は
きっと少なからずいるのではないかと思います。
●「叱る」と「怒る」の違い
「叱る」と「怒る」は違うとよく言われます。
上記の観点から、「叱る」と「怒る」を区別すると
こんな風にいえるのかもしれません。
「叱る」場合の理由は、
組織としての方向性に反したからということ、
「怒る」場合の理由は、
注意をする側の者の理論に反したからということ、
だと。
「叱る」ときには、「なぜ、注意をするのか」といえば、
組織として大事にしていること(理念)、
組織が目指す方向性、組織の目的・ビジョンに
反したからなのです。
もし、「なぜ、叱るのか?」と聞かれれば、その理由は、
組織としての理念や目的、ビジョンに反しているから
という理由でなければならないでしょう。
個人的に気に入らないからという理由であっては
決していけないはずです。
落合監督も、単にホームランを打たれて負けて、悔しいから
という理由だけで注意したのではないはずです。
これは企業組織においても同じでしょう。
部下や社員を叱る場合には、
組織としての理念や目的、ビジョンと照らし合わせ、
それに反した行動をとったから
という理由が必要になるはずです。
●大事なのは一貫性
もし、組織のリーダーが「怒る」ではなく、
「叱る」を徹底させていけば、
そこには間違いなく「一貫性」が生まれます。
なぜならば、
組織において大事なこと(理念)や
組織が目指す方向性や目的・ビジョンは
大きく変わることはないからです。
それが判断基準になって叱るのですから、
一貫性は生まれるでしょう。
怒る場合は、
自分の感情や自分の理論に反するからであり、
相手の好き嫌いで怒ったり、
自分の感情の起伏にまかせて怒ったりと、
一貫性は生まれません。
怒られる側も、
「なぜ、怒られているのか」
が分からないことになります。
たとえば、部下が時間に遅れてきたとします。
そのときに、叱るとすれば、
組織のビジョンなり理念なり、
方向性を引き合いに出すのです。
「しっかりと時間を守ってもらわなくてはいけない!
我々のビジョンは、
『お客様に地域NO.1の品質の評価を頂く』
だよね。
最高の品質を提供して、評価されようとしているのに、
遅刻をしてくるようでは、それは実現することはできないだろ!
これから遅刻しないようにして欲しい。」
とするのです。
決して、
「何遅刻しているんだ!そんなことでは、社会人として失格だぞ!」
といってはいけません。
それでは、上司の感情を処理するだけで部下としては、
恐らく納得はしないでしょう。
●部下も納得せざるを得ない
ムリムリにでも、組織の方向性を示して注意をすると
部下は納得せざるを得ないという、
上司にとってのメリットもあります。
組織が目指している方向性に反しているから注意するんだ、
という大義名分を得ているわけですから。
最後にちょっときつい言い方になるかもしれませんが、
もし、組織において上司が
組織としての理念やビジョン、方向性や目的・目標を知らないとしたら、
その上司は叱る資格がないともいえるのかもしれません。
それと最後のもうひとつ。
会社の方向性や、ビジョンや目的、目標などを
引き合いに出して叱ると、
もうひとついいことがあると思っています。
それは、会社の方向性やビジョンや目的などが
社員に浸透しやすくなるということです。
●まとめ
「“叱る”とは、
組織としての理念やビジョン、方針が背景にある。
“怒る”とは、組織の理由より個人の理由が優先される」。