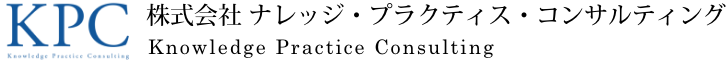そのコーチングが部下をダメにする!
先日お会いした、とある企業の管理者の方。
部下育成で、かなり悩んでいるようでした。
非常にまじめそうな方で、
もうちょっと気楽に考えてもいいのになぁ、
と思いつつ、話を聞いていました。
細かい話は書ききれませんが、
そのなかで出てきたことで、
なかなか興味深い内容のことがありましたので、
お伝えしたいと思います。
その管理者の方、部下育成のコーチングについて
こんなことをおっしゃっていました。
「コーチングを企業内研修で習ったんです。
質問をして、部下の考えを引き出す、
そのことは、分かります。
でも、それだけでうまくいかないときもありますよね。
いくら質問しても、答え出せない部下もいるし・・・。
その場合は、教えざるを得ないと思うんですよ。
どういうときにコーチングを使うべきなのか、
どういうときは教えればいいのか、
コーチングを学んで、逆に悩んじゃってますよ」。
なるほど、
「コーチングをするか、ティーチングをするか、
それが問題だ」ってことですね。
確かに、コーティングとティーチング(教える)の
使い分けは、難しいところです。
その場で、その管理者の方に、私から
お伝えしたのは、次のようなことでした。
「コーチングとティーチングを
分けて使う必要ないですよ。
コーチングとティーチングを融合して、
部下と話をすればいい。
例えば、30分間、部下と話をするというときに、
『よし、今からコーチングをしよう』と思うのではなく、
その30分間の間、瞬時にコーチングとティーチングを切り替える。
ハイブリッドな管理者になるイメージかな。
じゃあ、どのように瞬時に切り替えるかっていうと、
ティーチングして、そのティーチングした内容にコーチング、
コーチングして、部下が答えた内容にティーチング、
で行えばいいんです。
例えば、営業マンの部下に上司が話をするとしたら、
こんな感じ。
部下:A社の攻略がなかなか思うように進みません。
上司:なるほど、A社がうまくいってないのか?
(何がネックになっている等原因系を聞いたうえで)
そういうことであれば、いろいろ方法はあると思うけど、
例えば、○○を入口商品にして、
アプローチしてみるのもありかもね。
部下:なるほど、○○なら比較的敷居も低いし、
それを突破口にしていけるかもしれませんね。
上司:じゃあ、○○を紹介して関心を持って
もらわないといけないんだけど、
どんなことに気を付けて話をしたらいいかな?
○○を入口商品にしてみたら、というのは、
上司から部下へのアドバイス、ティーチング。
で、どんなことに気と付けてプレゼンしたらいいだろう?と
問いかけているのは、コーチングですね。
この逆もありです。
こんな感じ・・・。
部下:A社の攻略がなかなか思うように進みません。
上司:なるほど、A社がうまくいってないのか?
(何がネックになっている等原因系を聞いたうえで)
A社が今、我々のような会社に一番期待していることって
なんだろう?
部下:一番期待していることですか?
そうですね、コスト削減につながる提案でしょうか?
上司:確かに、それはあるね。
コスト削減につながる提案ってことで言えば、
長期的にその期待に応えていくためにも、
まず大きな話ではなく、○○を紹介して、
うちとの信頼関係を構築していくきっかけにするのもいいよね。
部下:なるほど。
上司:どうプレゼンしていこうか?
こんな感じで、コーチングとティーチングを
きっちり分けるのではなく、
ハイブリッドな感じで、やればいいんです。
部下も知識と経験がなくて、コーチングされても、
答えられないこともありますからね」。
以上、私からのコメント。
しかし、なぜ、このようにせっかくコーチングを
学びながら、こんな複雑に考えて、
コーチングを難し捉えてしまうのでしょう?
企業内でコーチング研修を行う講師の方で、
「コーチング至上主義」で、
コーチングが唯一の正しい部下育成手法、
のような感じで伝える方がいたりするんです。
これが一つの弊害になっている気はするんですよね。
また随分コーチングの専門的な細かい技法を
教えたりする講師の方もいるようです。
コーチングを専門にやっている方に多いんですが・・・
で、思うのは、管理職は別にコーチングのプロに
なりたいわけじゃないってこと。
会社側もコーチングのプロにしたいわけじゃない。
管理職が、コーチングを学ぶのは、
マネジメントのプロとして、そのレベルを
あげるためです。
管理者にとって、コーチングのスキルは、
めちゃくちゃ大事です。
コーチングできないのに部下育成できない、
ぐらいに思っています。
が、コーチング一つで部下育成がうまくいくわけではないです。
マネジメントのプロであるべき管理職を
コーチングのプロにするような内容の
コーチング研修、これが、なにかコーチングという手法を
複雑にして、管理者にとって難しいもの、使いにくいものに
させているような気がします。
もっと簡単にコーチングを捉えていいですよ。