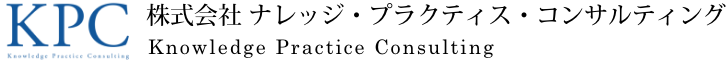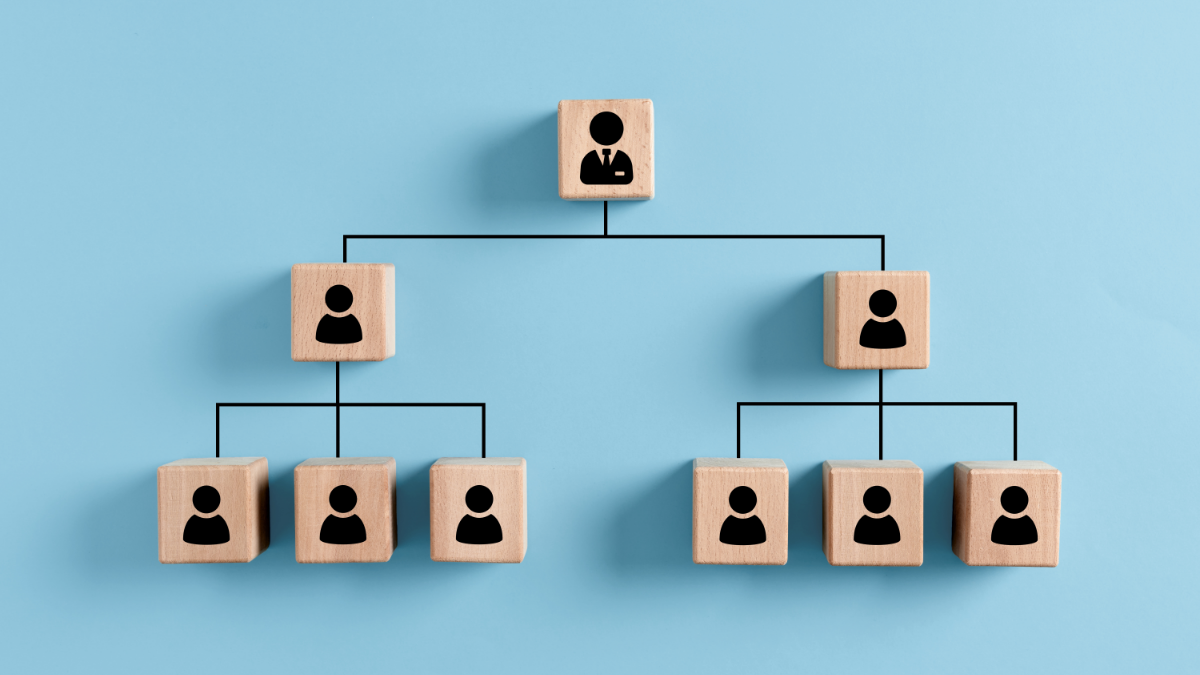心理的安全性の高い組織とぬるい組織の違い ~中日ドラゴンズに学ぶ
弱い!
もう、ひたすら弱いです・・・
中日ドラゴンズ・・・
1974年以来の中日ファンですが、
かつてないぐらいに弱い。
2025年7月9日時点で、
借金10、首位とは14ゲーム差。
試合を見ていても、
同じプロ野球チームとは思えない弱さ。
社会人野球の強豪、
トヨタ自動車や三菱重工と対戦したら、
簡単に負けてしまうのではないかと
思えるぐらいです。
一応、現時点でセ・リーグの6球団中5位なので、
最下位ではないです。
が、最下位のヤクルトスワローズは、
ここ数年は弱い状態が続いていますが、
それでも、強くなる期待感があります。
が、中日の場合、今後強くなる兆しも見えず、
ファンとしては、何を期待して応援すればいいのか、
ストレス、徒労感ばかりが募る状態です。
ということで、そのストレス発散のために
今回のブログを書かせていただきます。
その点、何卒ご容赦ください。
なぜ、中日はこんなに弱いのか?
なぜ同じプロ野球チームとして
これほど差がつくのか?
立浪監督時代(2022年~24年)の弱さの要因と
今の井上監督の弱さの要因は違っているように
感じています。
どちらかというと今の弱さは、
与田監督の時代(2019年~21年)の弱さの要因に
近いと思っています。
長年にわたり弱い状態が続いている
(2012年以来Aクラスは1度だけ)のは、
球団としての経営方針など
フロントの課題がかなり大きいとは思います。
しかし、今回のブログは
現場のマネジメントに焦点を当て、
「真に心理的安全性の高い組織」と
「ぬるい組織」の違いから、
今の中日ドラゴンズの弱さの要因を
考察したいと思います。
先日、こんな試合がありました。
7月2日の横浜スタジアムでの対DeNA戦。
先発は今季、エース格として期待された高橋宏斗。
先頭から三振とショートゴロで2アウト。
3番の宮崎敏郎選手に対しては、
フルカウントからサードゴロで
打ち取ったかに見えました。
ところが、打球は高いバウンドとなり、
サードの佐藤龍世選手は
ボールと照明が重なったのか捕球できず、
ランナーを出すこととなりました。
(佐藤選手は、6月17日に
パ・リーグの西武から
移籍してきたばかりの選手。)
普通に処理していれば、
1回の表は三者凡退だったところです。
その後、4番の牧秀悟選手にはヒット、
さらに5番の松尾汐恩選手にフォアボール。
満塁となって、6番の井上絢登選手には
スプリットをとらえられ、満塁ホームランで4失点。
初回のこの4点が重くのしかかり、敗戦・・・。
その試合後の井上監督のコメントです・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『それは…もう(佐藤)龍世、責められんからね。
横浜スタジアムはよくあることだからね。
まあ、『照明が入った』ってところは
現役のころとかも知ってるし、三塁手も結構あるから。』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これはもう弱い組織のリーダーが言う
典型的なコメントだと強く強く思うわけです。
メンバーがミスをしたり、
成果を出せなかったときに、
「仕方がない」なんてリーダーが
言う組織は強くなれません。
真に「心理的安全性のある組織」と
「ぬるい組織」の違いは、
特にチームとして成果が出せなかったときや
メンバーがミスをしたときに
現れると考えています。
心理的安全性のある組織はこうです。
成果が出ていないのはなぜか、
今回ミスをしてしまったのはなぜか、
どうしたら改善できるか、
どうしたら二度と同じミスを繰り返さなくなるか、
自分の意見や考えを伝えあい、
徹底的に話し合う。
もちろん、そこには以下のような
恐怖はありません。
発言しても、
「こんなことも知らないの?」と
無知を指摘されることの恐怖、
「あなたの能力・スキルが
ないからこういうミスをした」
と無能を指摘される恐怖、
「お前の言っていることは的を射てない」とか
「あなたの意見なんて誰も聞いてくれないよ」とか
「こんなミスをする人間はうちのチームに必要ない」と
邪魔者扱いされる恐怖、
「そんな細かいことを気にするなんて、
後ろ向きな思考の人だね。前向きにいこうよ」と
ネガティブに思われる恐怖、
こうした恐怖を感じず、話し合える。
もちろん、ミスや失敗の原因を
個人のせいにすることもありません。
組織全体で思うことを言い合って、
同じ失敗を繰り返さないようにする、
それが真に心理的安全性のある組織です。
ぬるい組織は、これができない。
成果が出せていないこと、
ミスしたことについて
「こういうこともある、
次に成果を出せばいいよ」とか
「まあ、気にせず次頑張ろう」とか
「これは誰も責められない、仕方ないよ」とか
耳障りのいい言葉を言って、
そのミスや失敗を活かそうとしない。
そこから何も学ばない。
中日の事例でいえば、
試合の敗因を分析すれば、
このサードが捕球できなかったこと
(記録はヒットですが)は
大きな敗因の一つのはず。
もちろんその後、ヒットとフォアボールを許し、
満塁ホームランを打たれた高橋宏斗も悪い。
しかし、それでも大量失点の
きっかけになったのは、
サードの佐藤龍世のミスです。
それを仕方がないと言っていては
『ぬるい組織』なのです。
リーダー自らがぬるい組織にしてしまっている。
今までの話をマトリックスでまとめると
こんな感じでしょうか?
それと、この試合後の高橋宏斗投手の
コメントは以下の通り。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「初回のプレーは仕方ない。
(佐藤)龍世さんは試合中、守備で助けてくれた。
それよりも、あの後につながれてしまった僕が悪い」
「(2回以降は持ち直したものの)
今、僕は全く信頼がない投手。
一から信頼を積み重ねていくしかない」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんか相手の気持ちを慮りすぎて、
無理に自責の言葉を
使っている気すらしてきます。
例えば、以下のように言ってこそ
強いチームなのかもしれません。
『私は、投手としての責任を全うします。
野手もその責任を全うしてほしい。
その責任が全うできなかったあの場面で、
何があのミスの原因だったかを
徹底的に考えて、再発を防いでほしい。』
これが選手同士で言えたらいいとは思いますが、
さすがにこれを言ったらギスギスしそうです。
であれば、コーチなり監督が
ちゃんと再発防止のための話し合いができる場を
設けることが必要になるでしょう。
横浜スタジアムでよくあることと分かっているなら、
内野守備走塁の堂上コーチが、
なぜ、その情報を西武から移籍してきて間もない
佐藤龍世にしっかりとブリーフィングして
おかなかったのか?
今回のミスを防げていたとしたら、
何をしておけたらよかったのか?
そこをしっかりと考えなかったら、
今後も同じ失敗を繰り返してしまうと思います。
で、また仕方がないで済ませる。
これでは経験から学び、
成長する組織にはなりません。
少し古い話になりますが、
日本サッカー代表の監督に
森保一氏が就任した当時、
チーム運営の方針に関し、
テレビで以下のような発言が
取り上げられていました。
「選手にかみなりを落とさない。
『あの局面ではどうしたら良かった?』
問題を投げかけ、選手同士で解決させる」
ミス・失敗に対して、個人を責めることなく、
でもそのミス・失敗から
組織としての学びを得るために、
徹底的に言い合える場を作る、
それが心理的安全性のある組織。
失敗を仕方ないで済ませて、
失敗から学びを得ようとしないのがぬるい組織。
最後に、この違いはどこから生まれるのかを
考えてみたいと思います。
これは、成果に対する執念の違いから
来るのではないかと考えています。
プロ野球で言えば勝つこと。
企業で言えば利益を出すこと。
さらに言えば、その成果への執念は
どこから生まれるかと言えば、
人を喜ばせたいという想いの強さ
からではないかと思っています。
要は中日ドラゴンズの場合、
ファンを喜ばせたいという気持ちがなさすぎる
のではないかと思うのです。
勝つことが最大のファンサービスと言っていた
落合元監督の言葉はまさに的を射ていると思います。
ぬるい組織はお客さまや世の中の人たちを
喜ばせようというよりも、
組織内でお互いが傷つかないように
することを優先させる風土が
あるのではないでしょうか?